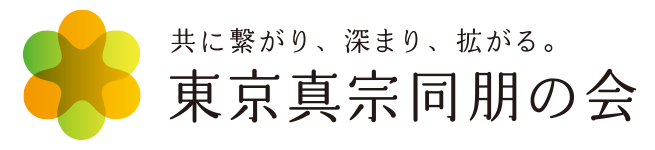まくはり会

日 時
毎月第3水曜日 午後2時~4時30分
会 場
真宗大谷派了善寺(東京都港区芝1-13-22)
浜松町駅(JR山手線、京浜東北線)
田町駅(JR山手線、京浜東北線)
大門駅(都営大江戸線、浅草線)
※会場とオンライン(zoom)の二形式で開催
講 師
百々海 真 氏(了善寺住職)
勤行、輪読(宮戸道雄著『仏に遇うということ』樹心社 ※コピーを配布)、法話、座談会
会のはじまり:2006(平成18)年10月に千葉方面会まくはり会として発足。会の名称は、かつてJR「海浜幕張駅」近くの「幕張テクノガーデン」を会場に開催していたことに由来。現在は講師の自坊に会場を移して開催。
サムドラの会


日 時
偶数月 土曜日
会 場
東京大学仏教青年会ホール
(東京都文京区本郷 3-33-5三菱UFJニコス本郷ビル 2F)
本郷三丁目駅(東京メトロ丸の内線、都営大江戸線)
※会場とオンライン(zoom)の二形式で開催
講 師
海 法龍 氏(神奈川県横須賀市長願寺住職)
勤行、法話、座談会
会のはじまり:1989(平成元)年に開設された聞法会が前身となり、1996(平成8)年開設。現講師の海氏を迎えた法座として2001年から開かれている。2008年2月に現在の「サムドラ」(サンスクリット語で「海」の意)と名を改めた。
曽我量深に学ぶ

日 時
隔月第月曜日 午後2時~4時30分
会 場
真宗大谷派親鸞仏教センター(東京都文京区湯島2-19-11)
本郷三丁目駅(東京メトロ丸の内線、都営大江戸線)
湯島駅(東京メトロ千代田線)
※会場とオンライン(zoom)の二形式で開催
講 師
齊藤 研 氏(新潟県三条市 正樂寺住職)
勤行、法話、座談会、
テキスト:曽我量深講話録1(曽我量深著、大法輪閣)
会のはじまり:曽我先生の深く独創的な思索が表された言葉をとおして、先生のいただかれた親鸞聖人の教えにふれ教えに学び、集うた人々がその受けとめを共有する機縁となることを願い、2025年に開設。
あきば会


日 時
毎月第3火曜日 午後1時30分~3時30分
※講師、会場等の都合で変更の場合有。
会 場
名響寺(千葉県市川市伊勢宿18-7)
行徳駅(東京メトロ東西線)
講 師
岩松 知也 氏(茨城県古河市浄善寺住職)
勤行、輪読(井上尚実著『はじめて読む正信偈』東本願寺出版)法話、座談
会のはじまり:閉会した東船橋の聞法会が前身となって2005(平成17)10月からJR「秋葉原駅」近くの貸会議室を会場として発足。その後、新型コロナウイルス対策として都内での移動回避のため、2020(令和2)年11月から会場を名響寺に移した。
哲学堂地区会

日 時
毎月第3金曜日 午後1時~4時(1月、7月は休会)
※参加者都合で金曜日以外の開催有。
会 場
真宗大谷派顯真寺(東京都豊島区南池袋4-20-1)
東池袋駅(東京メトロ有楽町線)
東池袋四丁目(都電荒川線)
講 師
近田 聖二 氏(顯真寺住職)
勤行、法話(現在は蓮如上人御一代記聞書がテーマ)、座談
会のはじまり:1966(昭和41)年開設。かつては、会名のとおり中野区にある井上円了に縁のある「哲学堂」を会場としていた。2013(平成25)年から会場を現在の顕真寺に変更して開催している。
城南地区会

日 時
毎月第3木曜日 午後2時~4時
会 場
zoomのみで開催
講 師
市野 潤 氏(市川市道誠寺)
輪読(鶴田義光著『歎異抄講述・聞書2』響流書房)、法話、座談会
会のはじまり:1963(昭和38)年に西小山(品川区)地区会として開設され、横浜市内の会議室などで開かれてきた。2020(令和2)年2月からzoomを利用して開催されている。
坂戸の会


日 時
隔月第1月曜日 午後1時30分~午後4時
会 場
坂戸市立坂戸駅前集会施設(埼玉県坂戸市日の出町16-11)
坂戸駅(東武東上線、東武越生線)
講 師
【偶数月】嵩 海史 氏
【奇数月】埼玉県内僧侶
大谷 一郎 氏(東松山市遊了寺)
春近 敬 氏(春日部市皆念寺)
佐々木 弘明 氏(本庄市西廣寺)
寺本 智真 氏(東京教区駐在教導)
洲﨑 善裕 氏(東京教区駐在教導)
法話(偶数月は正信偈をテーマとし、奇数月は広く真宗全体をテーマとする。)、座談会
会のはじまり:2017(平成29)年に、これまで当会の法座がなかった埼玉県の中部でも聞法する場をとの発起人の声により開設された。その熱意に講師が応えられ、歎異抄を学ぶ法座としてスタート。2023(令和5)年より奇数月に埼玉県内の僧侶を招いて仏教全般、真宗全般についての法話をいただく毎月の会座となった。
市川船橋地区会


日 時
毎月第3火曜日 午後1時30分~午後3時半
会 場
名響寺(千葉県市川市伊勢宿18-7)
行徳駅(東京メトロ東西線)
講 師
湯口 暁 氏
(首都圏教化推進本部本部員・東京真宗同朋の会事務局)
勤行、輪読(吉元信暁著『和讚の響き―親鸞の声を聞く』東本願寺出版、東本願寺出版)、座談会
会のはじまり:1990(平成2)年に海神地区会(千葉県市川市)として聞法会が開かれた。千葉県北西部に点在していた法座が閉じられていく中、市川市の施設を会場に市川船橋地区会「『歎異抄』に学ぶ会」が開かれた。2018(平成30)年に名響寺に会場を移し、『歎異抄』、本尊、浄土真宗の教え、真宗の仏事といった内容を手掛かりに聞法を続けている。
暁の会

日 時
毎月1回 午後1時~午後4時
会 場
会員自宅
会の内容
輪読、座談会
会のはじまり
2014年(平成26年)に、櫟暁氏とともに聞法された方々により、櫟氏が自坊(九州)に戻られた後も継続した聞法の場を持ちたいという願いのもと始まる。
光明の会

日 時
毎週日曜日 真宗会館日曜礼拝後~午後3時
会 場
東本願寺真宗会館(東京都練馬区谷原1-3-7)
高松三丁目バス停(西武バス)
講 師
雲井 一久 氏(神奈川県横浜市真照寺)
会の内容
法話(隔月)、輪読(清沢満之著『精神主義』東本願寺出版、『現代の聖典』東本願寺出版)、座談
会のはじまり
2003 (平成15)年に発足した真宗会館2階食堂で始まった自主的な法座「清沢満之輪読会」を由来とし、その参加者によって聞法会『光明の会』が発足。2022(令和4)年から横浜市真照寺の雲井先生を隔月で招いて法話をいただいている。
わだちでブッダ


日 時
毎月第1土曜日 午後3時~4時
会 場
とんかつれのん(千葉県松戸市新松戸1-374-1政和ビル地下1F)
新松戸駅(JR常磐線、武蔵野線)
幸谷駅(流鉄流山線)
講 師
不二門 至淨 氏(流山市流山開教所・首都圏教化推進本部本部員)
前田 義朗 氏(柏市淨眞寺)
長尾 朋聡 氏(市川市名響寺)
柏女 隆之 氏(松戸市因宗寺)
会の内容
法話、座談
会のはじまり
老いること、病を抱えること、死を迎えることなどをテーマに、仏教の話から生きるヒントを得たいと、会場のレストランのオーナーである世話人の発案がきっかけで、2022年7月に開設された。
謡曲教室(同好会)

日 時
毎月火曜日(月2回) 午後2時~5時
会 場
東本願寺真宗会館(東京都練馬区谷原1-3-7)
高松三丁目バス停(西武バス)
講 師
岩屋 稚沙子 氏(観世流能楽師)
会のはじまり
謡曲教室は、1992(平成4)年に開講され、2013年5月より現在の講師の岩屋稚沙子氏を迎えて継続されている。
講師より
正しい姿勢、はっきりした声を出す事は体にも心にもよいと思います。「謡」とは能の台本を謡うものなので、人間の本質に迫る内容のものが多く、理解を深めたいと思っています。