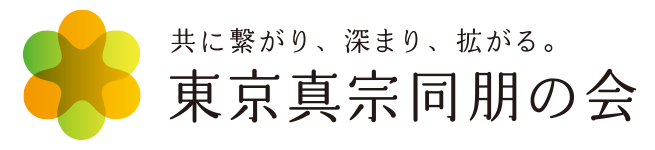ある日、真宗会館のお朝事に行くと、バックヤードで法務員が仏華の生け込みをなさっていた。次にお目にかかった際、その話題になり、生け込みが夕方までかかつたことを知る。他のお勤めもある中、それは大変なご苦労だろうと感じ、以前、草月流を20年弱習っていた私は、少しはお役に立てるのではないかとお手伝いを申し出た。
数カ月後、生け込みをご一緒させて頂く機会を得、そこで初めて、仏華の源流が池坊であることを知った。そういえば、親鶯聖人ゆかりの地の一つである六角堂を訪れた際、隣接するビルが池坊会館だったような…。
そして私は2021年12月から池坊を習い始めることになるのだが、テキストを読むと、文章の隅々に仏教の教えに通ずるものを感じた。通ずるどころか、仏教そのものではないか! ?それもそのはず、池坊の家元は、代々、六角堂の住職(ちなみに宗派は天台宗)なのだそうだ。若い頃、型にはまった生け方に馴染めず、比較的自由な発想の草月流を選んだ私であったが、今は池坊の精神がとてもしっくりきている。
池坊では、本部講師が全国で生け込みのデモンストレーションをしてくださる「巡回講座」を実施している。講座では、講師が10杯前後の生け花を生け、そのうち5杯ほど受講者に花器ごとプレゼントされる。生け花のほか、月刊誌や講師からの特別な品もある。
先日、東京お茶の水で開催された巡回講座を受講した。生けながら様々な解説をして頂き、生ける際のヒントも沢山頂いた。しかも、抽選会では、月刊誌が当たったのである!初心者である私には、とてもうれしい品だ!
月刊誌は2種類(「かどう」と「ざいけ」)あり、そのうち1種を半年間無料で頂ける。“かどう”は分かるが、“ざいけ”は在家? 「かどう」は上級者向き、「ざいけ」は比較的優しい内容だ。さすが「在家」向けの冊子だなと感心し、ペラペラと見本のページをめくってみると写真の分量が多く、見ているだけでも楽しい。
私は出家しておらず(僧侶の資格はない)、在家信者であるから、ここは迷わず「在家」を選んだ。ちなみに見本は2種類とも頂くことができた。
さて、帰宅して2つの冊子のタイトルをよく確認してみると…、ひとつは「華道」、もう一つは「THE IKENOBO」と書いてあるではないか。どうやら「ザ・イケノボウ」を省略して「ザイケ」と呼ぶようである…。
「在家」だと思い込んだ私の笑える勘違いであったと反省。そして、真宗は在家(門徒)も僧侶もともに聴聞し、同じ立場である宗派であることをすっかり忘れていた。
これは、僧侶ではないからと、いろいろと怠け心が生じていた最近の自分に、改めて気付かせて頂いた出来事であった。
南無阿弥陀仏
城北地区:藤原淑子(釈尼淑縁)