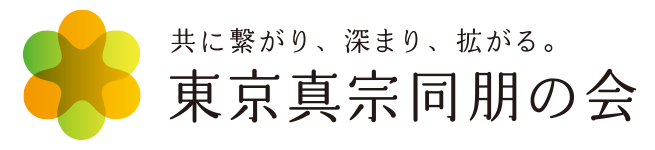昨年11月24日(日)、25日(月)の2日間、本山の報恩講にサンガネット報恩講奉仕団として参加させていただきました。奉仕団への参加は、コロナ禍前の2018年のお煤払い以来6年ぶりでした。これまでも本山の報恩講には、個人でお参りさせていただくことはありましたが、いつも一緒に聞法している僧伽の法兄のみなさまと同朋会館に寝泊まりしてお勤めしたり、座談をしたり、清掃奉仕をしたりしながら、報恩講に参拝できたことがとても嬉しかったです。
同朋会館から記念品と一緒に教化冊子『真宗の生活』の2025年版をいただいてきました。そのなかに九州大谷短期大学名誉学長古田和弘先生の「お内仏ってなんですか?」という文章が掲載されています。
なぜ、お内仏が必要なのかという疑問について、古田先生は「私たちが真実をすぐに忘れてしまうからです。しかし、どんなに忘れようとも、家庭に本尊があれば、いやおうなしに目にとまります。」(『真宗の生活2025年版』3頁)と説明されます。この文章を目にしたとき、以前一人暮らしの自宅に、お内仏をお迎えしたときのことを思い出しました。
私の父は次男で、お寺とのお付き合いは伯父がしており、父の家(私の実家)にも、私の自宅にもお内仏はありませんでした。ご縁をいただき受式した帰敬式での「朝夕のお勤めを生活の基本とし」という誓いの辞(ことば)を口にした際、私にも似たような疑問が浮かびました。「さて、お勤めしようにも、どこを向いてお念仏しようか?本山の方向?本山よりも我が家から近いのは真宗会館だなあ…。いやいや、お浄士の方向じやないのか?」
聞其名号(もんごみようごう)、名号が阿弥陀さまだと分かっているつもりでも、古田先生の説明のとおり真実をすぐに忘れてしまうから「どこを向いてお念仏しようか?」という疑問が湧くのでしょう。とは言え、難しいことは考えず、1Kの自宅に納まる小さなお内仏をお迎えしたのが2017年の夏のことでした。以来、起床後お内仏の扉を開けてお念仏、夜帰宅したらお念仏して扉を閉めるお内仏の前に身をおく生活を送っています。
「どこを向いてお念仏しようか?」と思ったことも、そう思ってお内仏をお迎えしたのもすべて阿弥陀さまのおはからいなのでしょう。このようなことを思い出した同朋会館からのお土産でした。また、仕事の都合を付けて奉仕団に参加したいです。
南無阿弥陀仏
釈興教 藤江 亮介
敬 弔
宮島 ヒサ様(法名:無量院釋尼妙久) *2025年1月命終 満97歳
ご生前のご厚情に深く感謝するとともに念仏合掌して哀悼の意を表します。