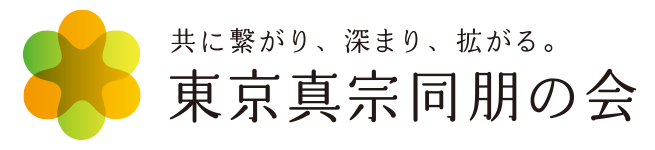私の東京真宗同朋の会への入会は昨年5月のことで、聞法生活を振り返ってみました。
以前、職場の配属で長らく名古屋に住んでおり、私は離郷門徒でした。真宗会館には年末年始に東京に帰省したときに初詣のように修正会〈しゆしようえ〉にお参りし、次の行事案内を耳に留めて名古屋に戻っていました。名古屋にも別院がありますが、このころはまだ聞法という言葉を知りませんでした。仕事で名古屋に来たので同僚のように手に職をつけようと思い、資格の勉強をしましたが、成果につながりません。休日が苦痛になり始めました。
ある年の修正会の後、東本願寺出版の販売サイトを見ていたとき、社会で生きる上での道標のようになりそうなタイトルの本がたまたま目に留まり、数冊取り寄せてみることにしました。
しかし読んでみると、内容が頭に残らない。
今思えば、何がわからないのかがわからないのです。それでは調べることも人に聞くこともできません。基本的な言葉もわからないので、理解に至らなかったのです。その話をする機会もなく積読となり、年月は過ぎていきました。
転勤で東京に戻ってきてからしばらくすると、休日に真宗会館に参拝するようになりました。感話や法話を聞いていると、どこか身に覚えのある話がありました。聞法会で他の方の話を聞いていると、私と似ている方がいることに気づきました。人の話を聞くと、私の状況が言語化されているかのようです。独学と違って私がわかっていないことが明らかになっていきます。真宗会館に限らず同僚や友人、面識のない人にも私と同じような方がいることに気づき始めました。SNSでの発信はおろか言葉にもなっていないのに、なぜだろう?
お内仏に向かって念仏していると、目の前にいるのは阿弥陀如来の絵像でした。今までずっと阿弥陀様は私を見ていました。
南無阿弥陀仏
釋求道 加藤 寛史